猫のマダニ対策をしていますか?
猫ちゃんを飼っている飼い主さんのほとんどがマダニ予防をしっかりと行っていることでしょう。
しかし、
また、飼い猫だけではなく
猫ちゃんにマダニが寄生することで、猫ちゃんが病気に感染してしまい、命を落としてしまうこともあります。
また、猫ちゃんから人間に感染してしまうということも起こりました。
災害時に避難所では必ずマダニ予防、対策が行われているか否かの確認が行われています。
そこで今回は災害時に猫ちゃんも同行避難をした先でしっかりと避難所に居ることができるように、マダニ対策の必要性ややり方避難所での流れ、必要なものなどを詳しくご紹介していきます。
SFTSの症状や危険性についても合わせてご紹介します。
猫ちゃんを飼う上で知っておかなければいけない重要な感染症です。
猫に寄生するマダニとは

猫に寄生するマダニとは、どんなものなのでしょうか。
猫にマダニが寄生する場所
猫にマダニが寄生する場所は
などが挙げられます。
草の先端でマダニが待機し、猫に寄生するチャンスを狙っているため、草が多い場所で寄生されてしまうことが多くなります。
寄生したマダニが孵化してしまう・・・
猫に寄生したマダニが孵化してしまうと吸血をします。
猫の血を吸うことで、ダニの体重や大きさは100倍にまでなります。
吸血を繰り返すために、ダニは猫ちゃんの耳や頭などの皮膚の薄い場所にくちばしを刺し固定するため、無理に取ろうとすると皮膚が破けてしまったり、皮膚にダニの口だけが残り皮膚病の原因になります。
猫に寄生するマダニが引き起こす病気とは・・・

猫に寄生したマダニが原因で病気になってしまうことがあります。
マダニが猫の血を吸うことで、貧血や皮膚炎になってしまうことがあるのです。
またそれ以上に恐ろしいものが、重症熱性血小板減少症候群(SFTS)という病気です
重症熱性血小板減少症候群(SFTS)の症状は?
猫がSFTSに感染した際の症状についてです。
重症熱性血小板減少症候群(SFTS)の治療法は?
有効な治療法が確立されていないと言われています。
しかし、対処療法として静脈点滴などを行ってもらうことができるため、早めに動物病院に受診するようにしましょう。
避難所で求められるノミ・ダニ予防記録

避難所ではペット同伴可能の避難所とペットの同伴避難は不可となっている避難所があります。
自治体の情報を活用し、お住いの地域の避難所はペット可なのか不可なのか確認しておくことが大切です。
また、同伴避難可能な避難所でも人間と一緒に避難所で生活する共同避難ができる避難所と、人間と猫ちゃんは別の場所で避難生活を送る別室避難になる形の避難所の場合があります。
他の多くの人、多くの猫ちゃんと避難生活を送らなければいけないことから、感染症がまん延してしまわないように、ノミ・ダニの予防記録やワクチン接種記録など健康証明書が求められます。
避難グッズに予防記録や証明書を!
避難グッズのひとつとして、ノミ・ダニ予防の記録やワクチン接種記録、健康証明書などのコピーを入れておくようにしましょう。
実際に予防をおこなっていても、証明するものがなければ避難所に入ることができないという場合もあります。
忘れずに準備をしておいてください。
猫のマダニ予防のやり方は?

猫のマダニ予防のやり方についてです。
猫のマダニ予防は毎月行います。
マダニ駆除薬の使用
マダニ駆除薬というものがあります。
スポットタイプやスプレータイプ、錠剤タイプのものが存在しています。
動物病院でも処方してもらうことができ、動物病院の薬を使用することで、1~2ヶ月ほどの効果が続くとされています。
市販の駆除薬もありますが、効果が60%ほどだと言われていたり全身に広がることへの弱さが懸念されているため、動物病院から販売されている薬を使用することをおすすめします。
動物病院によっては、マダニだけではなく、ノミやフィラリア、内部寄生虫を同時に予防や駆除してくれる薬を使用している場所もあるので、かかりつけの主治医に相談してみましょう。
ブラッシングで定期的に確認を行うことも大切
お薬を使用していても、マダニが寄生してしまうということはあります。
そのため、日頃から定期的にブラッシングを行うことで、マダニがついていないか確認してあげることが大切です。
外に猫を出さない
災害時に猫ちゃんと飼い主さんが再会できなくなってしまったり、命を落としてしまったりということがないように、日頃から猫だけを外に出してしまうのはやめましょう。
草むらや河原に猫だけでいってしまいマダニに寄生されてしまうことももちろんあります。
愛猫ちゃんの命を守るためにも、完全室内飼いを推奨します。
冬でも油断禁物
マダニは梅雨の時期や秋に活発になるのですが、通年を通して活動しています。
冬の寒い時期でも油断せずに予防を行いましょう。
猫が何歳からマダニ予防ができる?

では、飼い猫ではなく捨てられてしまった猫ちゃんを保護した場合などのマダニ予防についてです。
生後8週齢(生後2ヶ月頃から)
目安としては生後2ヶ月頃からダニの予防薬を使用することができます。
しかし、体重や月齢にあう子猫用の薬を選ぶ必要があります。
保護した猫ちゃんの場合、ダニ以外にも感染症になってしまっていることがあるので、一度早めに動物病院へ受診することが大切です。
その際にマダニ予防についても相談し開始可能かどうか判断を仰ぎましょう。
猫に寄生したマダニによる病気!SFTSウイルスは人間にも感染する!?

猫に寄生したマダニが引き起こす病気、重症熱性血小板減少症候群(SFTS)は人間にも感染することがあります。
人間に感染すると致死率が高いと言われている病気なのです。
実際に獣医師が感染し死亡してしまう・・・
実際に三重県の獣医師さんがSFTSに感染した猫の治療を行った後に亡くなってしまったという事例があります。
重症熱性血小板症候群(SFTS)に感染した場合の症状
人間がSFTSに感染してしまった場合
などの症状が現れます。
致死率は6.3%~30%という報告がある恐ろしい感染症です。
避難所で猫のマダニ予防がより厳しく管理される可能性も・・・

猫から人間に重症熱性血小板減少症候群(SFTS)が感染するという事例はとても少なく、今まではそこまで多くの人が重視していなかったとも言えます。
しかし、三重県で起こった事例を始めとし、各都道府県で猫のマダニによる感染が広がっているというニュースや猫を介してはいないが人間が直接マダニに噛まれたことでSFTSに感染したニュースなどが多くなっています。
そのため、災害が起こった場合に避難所でもマダニの予防を行っているかという確認は今以上に厳しく確認を取るということが考えられます。
猫ちゃん、飼い主さんの命を守るためにもマダニ対策をしておくことはとても大切ですが、避難所での他の猫ちゃんや他の人のためにも必ず行っておき、記録を残しコピーを避難グッズのひとつにしておきましょう。
まとめ

いかがでしたでしょう。
ノミ・ダニ対策は飼い主さんの義務だといっても過言ではありませんね。
罰則などはないとはいえ、愛猫と飼い主さんを守るためにも、マダニ予防はとても重要だと言えます。
また、飼い猫で室内飼いなのに、SFTSに猫ちゃんが感染してしまったという事例もあります。
外に出すことがないからといって対策を行わないのではなく、しっかりと毎月の予防しておくことが大切ですね。
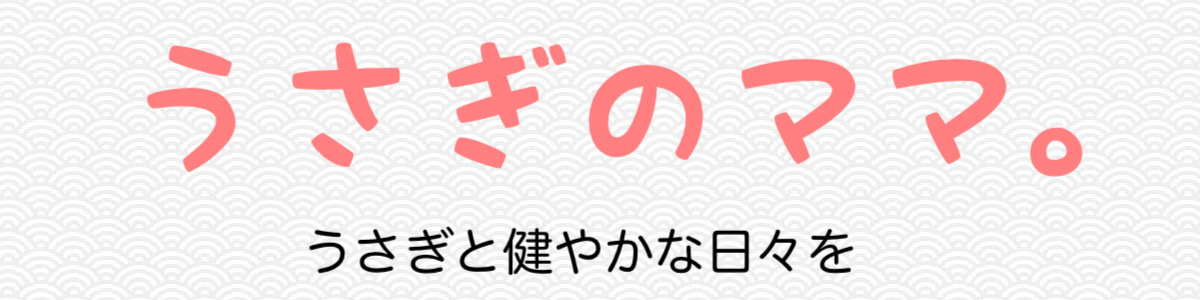
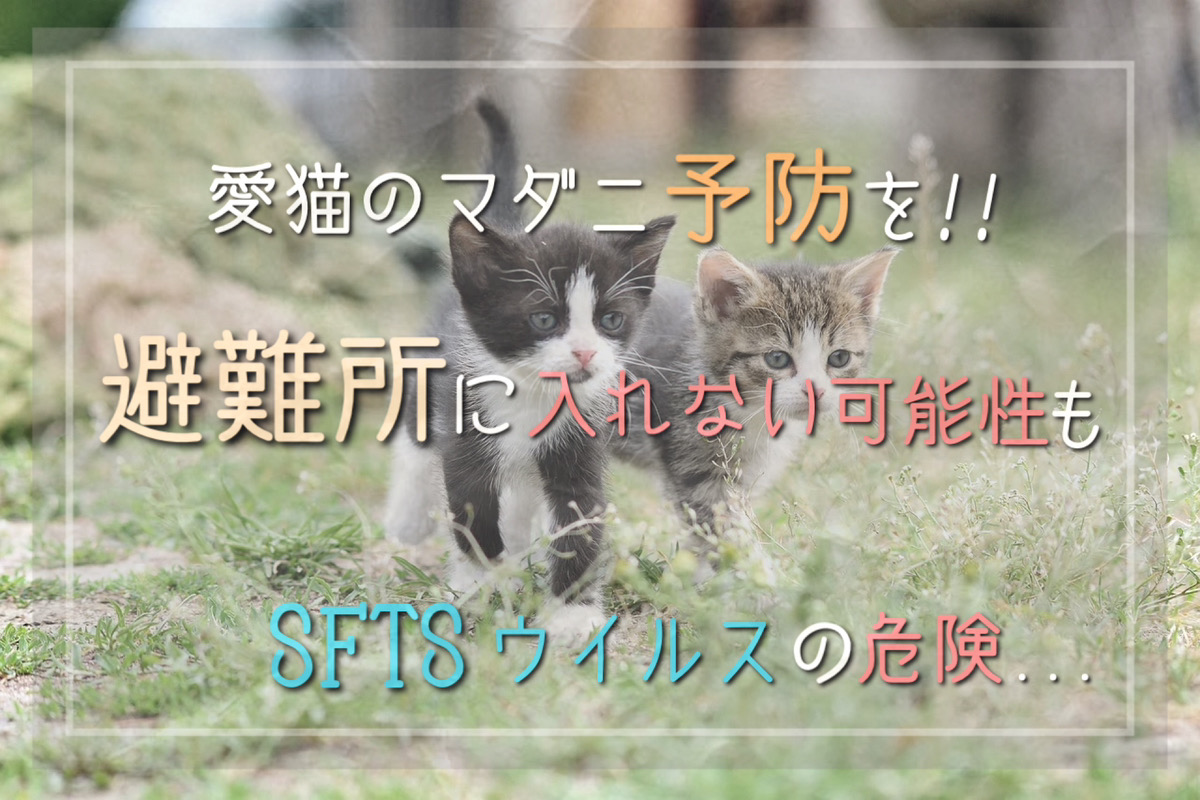
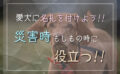

コメント